~わかりやすく伝わる文章・会話の黄金ルール~
構造化コミュニケーションに関する統計データ
出典:ビジネスリサーチラボ「構造化面接の効果」 東北大学「コミュニケーション能力と階層差」 グローバル・コミュニケーションセンター「AI技術を用いた会話構造の可視化」
言葉の引き出しを活かすには「構造化」が必要
「語彙力を増やしても、うまく伝わらない…」と感じたことはありませんか?
それは「構造化」が不足しているからです。
構造化とは、話す順番・書く順番を整理し、聞き手や読み手にとって理解しやすい形に整えること。
この記事では、初心者でも実践できる「構造化の3ステップ」を具体例とQ&Aつきで解説します。
段階1:型を使って話す・書く
型を使うと伝わりやすくなる理由
構造化の最初のステップは 「型(フレームワーク)」を使うこと。
話や文章を型に当てはめるだけで、論理が整理され、伝わりやすさが一気に高まります。
よく使われる構造化の型
- PREP法(結論→理由→具体例→結論)
- SDS法(要約→詳細→まとめ)
- 三段論法(主張A→主張B→結論C)
実践例(PREP法)
「この本はおすすめです(結論)。なぜなら文章力を鍛える実例が多いからです(理由)。実際に私も語彙力が伸びました(具体例)。だからおすすめです(結論)。」
Q&A 段階1
- Q1PREP法を使うと堅苦しくならない?
- A1
最初は堅く感じますが、聞き手にとっては「筋が通っていてわかりやすい」と好印象です。
- Q2型を意識すると話がぎこちなくなる…
- A2
練習を重ねれば自然に馴染みます。まずは型どおりに徹底し、慣れてきたら崩してOKです。
段階2:全体像を先に示す
なぜ全体像が必要なのか?
相手にとって「何をどの順で聞かされるのか」が分かっていると、安心して最後まで集中できます。
実践例
- 会話:「今日は3つ伝えたいことがあります。まず〜、次に〜、最後に〜です。」
- 文章:「本記事では①言葉の引き出しを増やす方法、②構造化のステップ、③失敗回避のポイントを紹介します。」
実践ポイント
- プレゼンでは冒頭で「3つのポイント」を提示する
- ブログ記事では「目次」「ステップ形式」を活用する
Q&A 段階2
- Q3短い会話にも全体像は必要?
- A3
必要です。たとえば「2つだけ言わせてください」と前置きするだけで、伝わりやすさが格段に向上します。
- Q4全体像を示すと話が長くならない?
- A4
むしろ逆で、相手が「あとどれくらいで終わるか」を予測でき、集中して聞いてくれます。
段階3:要点を整理して伝える
要点整理の重要性
情報が多すぎると相手は混乱します。3つ程度の要点にまとめると、理解と記憶に残りやすくなります。
実践例
- 商品紹介:「おすすめする理由は価格・品質・サポートの3点です。」
- 日常会話:「今日の出来事は仕事・家族・趣味、この3つです。」
実践ポイント
- 話す前に「要点3つ」をメモする
- 文章は1見出し=1テーマを意識する
Q&A 段階3
- Q5要点を絞ると説明不足になりませんか?
- A5
詳細は後から補足で十分。まずは「核」だけを届けることが大切です。
- Q6要点を整理しても脱線してしまう…
- A6
「3つの要点」を手元に書き出し、話が逸れたら戻る意識を持つと改善できます。
まとめ:構造化で伝わる力が劇的にアップする
「語彙力」と「構造化」を組み合わせると、表現力が格段にレベルアップします。
- 段階1:型を使う
- 段階2:全体像を示す
- 段階3:要点を整理する
これを意識するだけで、会話も文章も「分かりやすい!」と評価される人になれます。
次のステップに進む👉 ステップ4:アウトプットの場を増やす
前のステップに戻る👉 ステップ2:言葉の引き出しを増やす
この記事を読む👉 【初心者必見】言語化力を高めて全てを上手くいかせる完全指南書|5ステップ+失敗回避Q&A+チェックリスト
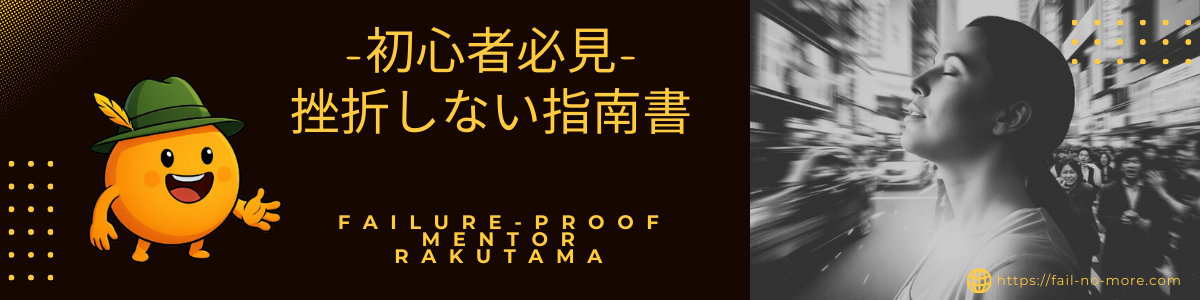
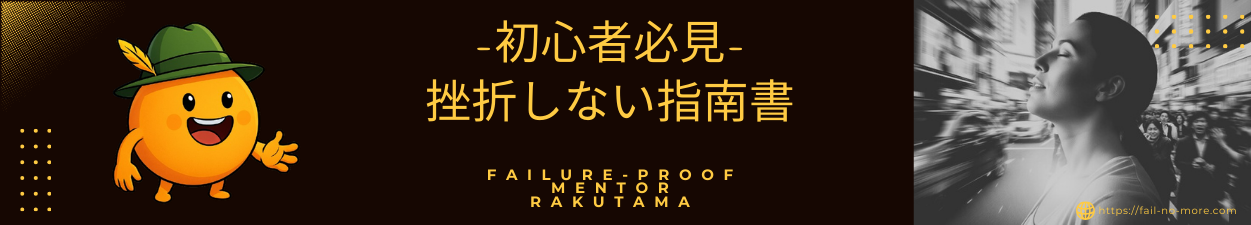



コメント