災害時に最も不安になるのが「家族や友人と連絡が取れない」状況です。地震や台風、洪水などの災害では、電話回線やインターネットが混雑し、通常の連絡手段が使えなくなる可能性 があります。
災害時の連絡方法に関する統計データ
| 項目 | データ・数値 | 備考・解説 |
|---|---|---|
| 災害時に家族と連絡方法を決めている人の割合 | 約33%(3人に1人) | 2023年調査。年代別に10代は最も高く、30代が低い傾向。 |
| 最も多い連絡方法 | スマホ・携帯電話の通話(約70%前後) | 次いでメール、SNS音声通話、災害用伝言板など。 |
| 家族との安否確認方法(上位3) | ①災害用伝言ダイヤル 41.2% | ②携帯災害用伝言板サービス 39.8% |
| ③遠くの親戚・知人を中継役にする 29.7% | ||
| 避難場所の位置を確認している人 | 約41.6% | 全国平均。防災意識向上の課題として捉えられている。 |
| 災害時の近隣との連絡・協力ができている人 | 約14.1% | 全国的にコミュニケーションが不足している現状。60代が最も高い。 |
| 災害情報の主な取得手段 | 携帯通話、地上波放送、SNS(LINE等) | 発災時~復旧期を通じて利用されている。 |
出典:モバイル社会研究所 災害時の連絡手段調査2024 内閣府 防災に関するアンケート調査 PDF 全労済 防災・災害意識調査2024 総務省 災害時情報伝達に役立つ手段(2017年) 総務省 情報通信の在り方調査(PDF) モバイル社会研究所 災害情報取得方法(年代別)
この記事では、災害時に活用できる連絡方法を整理し、家族や近隣との安否確認を円滑に行うためのポイントを紹介します。
1️⃣ 災害時に通信が混雑する理由
- 通常の数十倍の通話が集中するため、回線が制限される
- 停電や基地局の被害で電波が届きにくくなる
- 長時間の利用によるバッテリー切れのリスク
💡 ワンポイントアドバイス
災害発生直後は電話を避け、優先度の高い連絡に回線を譲ることが重要です。
2️⃣ 緊急時に使える連絡手段
📞 電話(音声通話)
- 最も使われるが、災害時は混雑しやすい
- 短時間の要点だけを伝える「ワンフレーズ通話」が有効
📩 SMS(ショートメッセージ)
- 通話よりも混雑が少なく届きやすい
- 文字数が限られるため「無事・避難済・場所」など簡潔に
📡 災害用伝言ダイヤル(171)
- 固定電話や公衆電話から利用可能
- 自分の番号に録音 → 家族が再生して安否確認できる
🌐 災害用伝言板(Web・キャリア提供)
- 携帯キャリア(NTTドコモ・au・ソフトバンクなど)が提供
- 携帯番号を検索して安否を確認できる
💬 LINEやSNS
- データ通信が使えれば連絡可能
- LINE「安否確認機能」やグループチャットが有効
- バッテリー消費が大きいため短文・低頻度で
💡 ワンポイントアドバイス
写真や長文メッセージよりも「短文+位置情報」が効率的です。
3️⃣ 家族で決めておくべきルール
- 連絡手段の優先順位を決めておく
→ SMS → LINE → 電話のように順番を設定 - 集合場所・避難先を事前に共有
→ 「自宅が危険な場合は〇〇小学校へ」など明確に - 遠方の親戚を「連絡の中継役」に
→ 被災地外の人を通じて安否情報をまとめる - 定期的な防災訓練に組み込む
→ 実際に家族で「伝言ダイヤル」を体験しておく
4️⃣ 近隣との連携の重要性
- ご近所同士で安否を確認し合う
- 高齢者や子ども、障害のある人を優先してサポート
- 町内会や自治体の防災ネットワークを活用
💡 ワンポイントアドバイス
家族が離れている場合でも、地域の助け合いが命を守ります。
関連記事リンク
防災マニュアルの記事はこちら
👉防災マニュアル|総合ページ
避難準備・持ち出し品のチェックは
👉非常持ち出し袋の準備|災害時に必要な持ち物まとめ
あなたの地域の避難場所を確認する方法
👉 避難場所を確認しよう|防災マップ活用法
まとめ
災害時の連絡方法は「普段の延長」で考えると失敗しがちです。
音声通話だけに頼らず、SMS・災害用伝言サービス・LINEなど複数の手段を準備し、家族でルールを決めておくことが安心につながります。
最も大切なのは、「どんな状況でも家族や仲間とつながるための準備をしておくこと」。それが生存率を高め、復旧への第一歩となります。
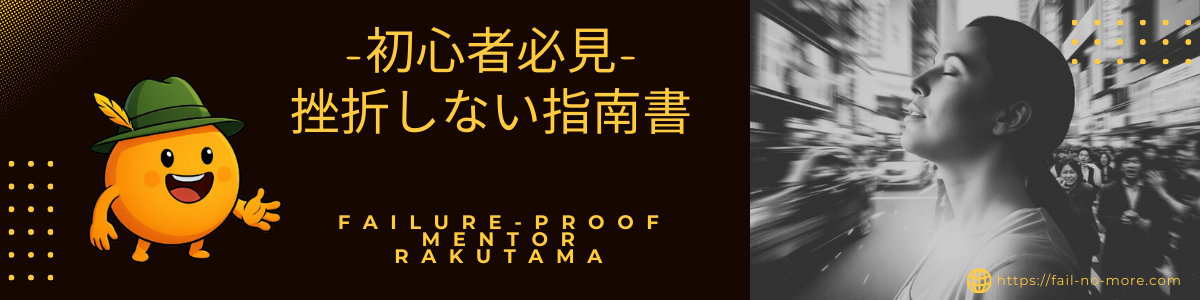
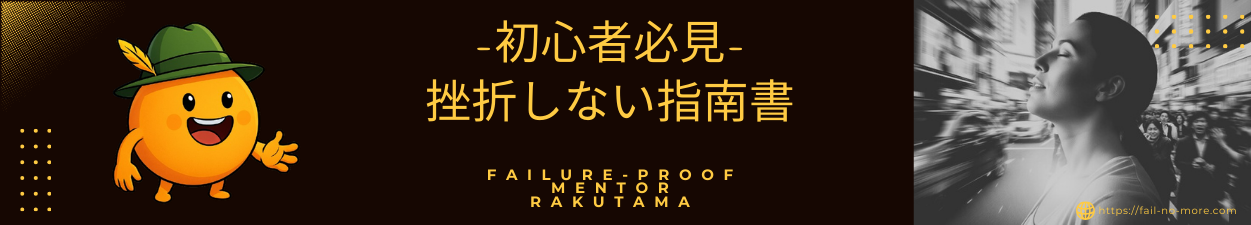



コメント